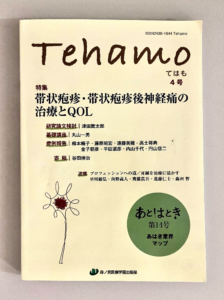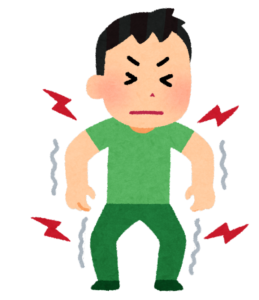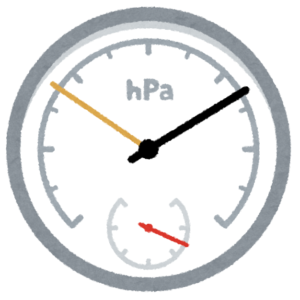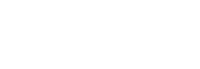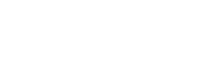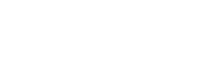2023年は癸卯(みずのと・う)!
東洋医学では、「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の十干と、「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の十二支の組み合わせで、「甲子」から「癸亥」までの60年周期で考える思想があります。

《十干(じゅっかん)》
甲(きのえ):木の兄 / 乙(きのと):木の弟
丙(ひのえ):火の兄 / 丁(ひのと):火の弟
戊(つちのえ):土の兄 / 己(つちのと):土の弟
庚(かのえ):金の兄 / 辛(かのと):金の弟
壬(みずのえ):水の兄 / 癸(みずのと):水の弟
《十二支(じゅうにし)》
子(ね) / 丑(うし) / 寅(とら) / 卯(う) / 辰(たつ) / 巳(み) /
午(うま) / 未(ひつじ) / 申(さる) / 酉(とり) / 戌(いぬ) / 亥(い)
2021年は辛丑(かのと・うし)、2022年は壬寅(みずのえ・とら)でした。2023年は癸卯(みずのと・う)です。
「癸(みずのと)」は十干の十番目で最後です。
「癸(みずのと)」は、「ひとまわり」「回転」「転換期」という漢字の意味を持ち、世の中が次の10年にうつるという意味になります。
ほかにも、「一揆(いっき)」の「揆(き)」にも通じ、人々の不平不満が爆発するという意味もあります。
また、十二支の「卯(う)」は、漢字の音読みでは「卯(ぼう)」です。植物の「茅(かや)」を意味する「茆(ぼう)」の意味があり、茅が繁茂するという意味の「茂(ぼう)」の意味があります。
「繁茂する」つまり、繁栄する意味もありますが、茂りすぎると身動きがとれなくなるため、「卯」の年は、雑草の生い茂った未開の土地を開墾・開拓する年になります。
木・火・土・金・水の五行では、「癸(みずのと)」は陰の水であり、冬の終わりという意味です。
「卯(う)」は陰の木であり、春の兆しを意味し、冬の寒さが終わり、春の兆しがはじまるイメージがあります。
つまり、新しい時代の転換期を意味し、新しいチャレンジをするべき時期になります。
また、中国伝統医学の五運六気理論は、十干十二支から気候と病気を予測します。
2023年癸卯は、陽明燥金司天・少陰君火在泉、火運不及となります。つまり、一年の前半は燥が支配し、一年の後半は火が支配します。一年を通じては、木・火・土・金・水の火が弱る年になります。

2023年の1月末から3月末は、『聖済総録』という千年前の古典によると、「水が凍り、寒い雨が降ります。その病は、からだの中が熱くなって脹れ、顔面の浮腫、眠くなり、鼻水が出て、あくびが出て、吐き気がする症状が増える」と予測されています。
現代の言葉になおすと、花粉症の鼻水などに要注意ですね。
東洋医学では、漢方も鍼灸も花粉症の鼻水は得意な病気です。
漢方では、「水飲(すいいん)」という状態を治療する「小青龍湯(しょうせいりゅうとう)」という処方がよく使われます。これは、胃腸に余分な水がたまった状態であり、体内の余分な水を体外に追い出すような処方になります。
鍼灸では、花粉症に対しては、印堂(いんどう)という眉間のツボや、迎香(げいこう)という鼻の横のツボに鍼をよく使います。顔面の血液循環を改善し、鼻の詰まりに効果があります。
また、通天(つうてん)という頭のてっぺんにあるツボや、上星(じょうせい)という前頭部のツボに鍼を刺します。さらに風池(ふうち)や天柱(てんちゅう)というツボに鍼を刺して、首肩こりをとります。
1回の治療で、少し鼻の詰まり感が改善します。1か月ほど継続することで、体の免疫系が調整され、楽になります。ぜひ、お試しください。
神戸東洋医療学院付属治療院
早川 敏弘
********************
神戸 三宮で鍼灸といえば
神戸東洋医療学院付属治療院
********************
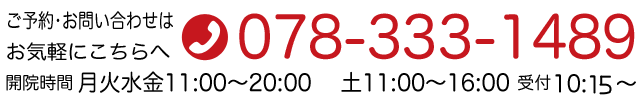
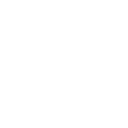
 皆さん年末年始はゆっくり過ごすことは出来ましたか。
皆さん年末年始はゆっくり過ごすことは出来ましたか。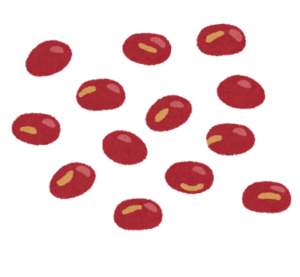 今回はそんな縁起の良い『小豆』の魅力についてお伝えしたいと思います。
今回はそんな縁起の良い『小豆』の魅力についてお伝えしたいと思います。 お腹に置いて、お正月の飲食で疲れた内臓の循環を良くしたり、冷えてしまった首肩には小豆の程よい重みと湿熱で血の巡りが良くなり疲れをとることが出来るのでおすすめです。
お腹に置いて、お正月の飲食で疲れた内臓の循環を良くしたり、冷えてしまった首肩には小豆の程よい重みと湿熱で血の巡りが良くなり疲れをとることが出来るのでおすすめです。