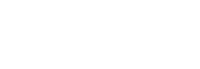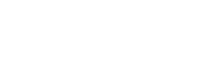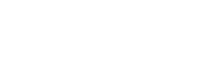冬とかゆみ
冬になると、冷たい風や室内の暖房によって肌が乾燥しやすくなり、それによってかゆみがひどくなることが多いです。
東洋医学では、このような症状を単なる皮膚の問題だけではなく、私たちの体の気血・津液のバランスと五臓六腑機能のバランスが崩れているとみています。
今回は東洋医学的にかゆみをどう考えているかについてお話しします。
<東洋医学的な原因>
① 肺の乾燥
東洋医学では、肺は皮膚と毛を司り、体内の津液を肌の表面に送り、しっとり感を維持させます。
冬場に乾燥した気である「燥邪(そうじゃ)」が強くなると肺が乾燥し、その結果、肌が荒れて引っ張られ、かゆみが起こりやすくなります。
これを「肺燥」といい、症状としては、乾燥した咳、喉の渇き、鼻の中の乾燥や皮膚の乾燥などです。
さらに皮膚の乾燥が進むと、角質が白く粉を吹いたような状態になります。
② 「血虚(けっきょ)」による肌の栄養不足
皮膚は、血液の栄養を通じて潤いを保ちます。
しかし、冬場の気温が低く、血行が悪くなったり、体質的に「血虚」(血液の栄養が不足している状態)の場合、皮膚が割れやすく、かゆみがひどくなることがあります。
特徴は、長く続く慢性的なかゆみ、夜間のかゆみ、皮膚のくすみ、手足の冷え症などの症状です。
③ 風と乾燥が結びついた「風燥(ふうそう)」
風は揺らして動く性質である「風邪(ふうじゃ)」。乾燥は、水分を乾かし皮膚や粘膜を傷つける性質である「乾邪(かんじゃ)」です。
冷たい風邪と、乾邪が結合した「風燥」の状態になると、体の水分を奪い、肌の表面に刺激を与えかゆみがひどくなります。
皮膚に発疹や赤い斑点ができやすいのもこのためです。
<東洋医学的な治療と、気を付ける習慣>
① 肺の乾燥によるもの
肺の乾燥を取り除くために、肺を潤すことを治療原則とします。
肺を潤す食べ物としては梨、蜂蜜、梅などがおすすめです。
避けるべき習慣としては、過度な暖房、辛い食べ物や揚げ物、飲酒、喫煙です。
② 血虚によるもの
この場合は血と気(エネルギー)を補い、循環を良くさせる治療を基本とします。
血を補う食べものはレバー、赤身の肉、黒豆、ほうれん草、トマトなどがあります。
気を付ける習慣は、過度なストレス、過労、長時間の同じ姿勢、睡眠不足です。
③ 風燥によるもの
風燥は津液が消耗されている状態なので、燥邪を取り除き、体内に不足している津液(体液、水分)を補うことを目指します。
津液を補える食べ物は、熟した梨、銀杏の実、蜂蜜、クコの実、大根などです。
日常生活中では白湯をこまめに飲むこと。また、部屋の湿度を適切に保ち、冷たい風に長時間当たらないように気を付けましょう。
上記以外にも、特にかゆみが強い方は、単に「水分を満たすこと」ではなく、「水分を守る」ことが大事です。
 保湿剤を選ぶ時は油分が十分なクリームや軟膏タイプがより良いです。
保湿剤を選ぶ時は油分が十分なクリームや軟膏タイプがより良いです。
特に入浴後3分以内に保湿剤を塗布し、角質が固く乾燥した部位はクリーム保湿後、オイルやバーム状の製品をもう一度塗り重ねて保護膜を作れば、水分保持力が高くなります。
入浴は 熱いお湯に長く浸かると、かえって肌の油分膜を洗い流して乾燥を悪化させる恐れがあります。
ぬるま湯で短く洗い、刺激の強い洗浄剤は避けた方が良いです。
シャワーの後もこすらず、軽く叩くように水気を取ってから、すぐ保湿剤を塗りましょう。
この冬、かゆみで悩んでいる方は保湿剤を塗るだけではなく、体内の気血・津液、五臓六腑の内部的なバランスが崩れないように鍼灸の施術を受けてみてください。
神戸東洋医療学院付属治療院
********************
神戸 三宮で鍼灸といえば
神戸東洋医療学院付属治療院
********************
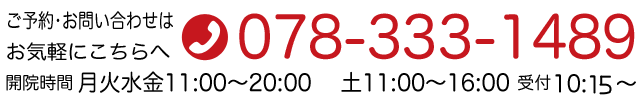
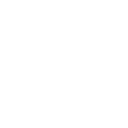




 3.眼精疲労の軽減
3.眼精疲労の軽減

 みなさんは、青魚の背がなぜ青いかをご存じですか?
みなさんは、青魚の背がなぜ青いかをご存じですか? このことから、ミトコンドリアが元気に活躍してもらう方が、私たちには有益だと理解していただけるのではないでしょうか。
このことから、ミトコンドリアが元気に活躍してもらう方が、私たちには有益だと理解していただけるのではないでしょうか。

 立つ・座るの動きを、「坐骨」から意識してあげると、太ももや腰への負担が少なくなりますし、
立つ・座るの動きを、「坐骨」から意識してあげると、太ももや腰への負担が少なくなりますし、 椅子に座っても、長座でも、三角座りでも、開脚でも、どの姿勢でも構いません!
椅子に座っても、長座でも、三角座りでも、開脚でも、どの姿勢でも構いません!