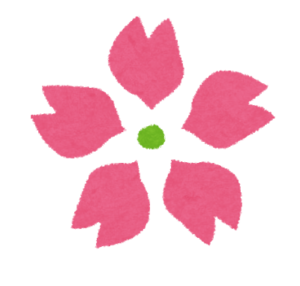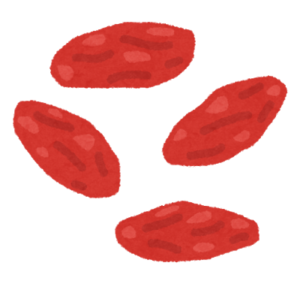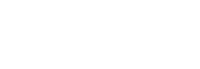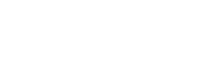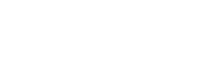梅雨型熱中症
小暑が近づき、これから最も暑い時期がやってきます。
今は梅雨真っ只中でジメジメと日を追うごとに暑さが増しておりますね。
今回は梅雨型の熱中症についてお話していきたいと思います。
 熱中症といえば、酷暑の中で起こるものが一般的と思われますが、実は気温が26℃程度でも、湿度が高い環境では熱中症リスクが高くなりますので注意が必要です。
熱中症といえば、酷暑の中で起こるものが一般的と思われますが、実は気温が26℃程度でも、湿度が高い環境では熱中症リスクが高くなりますので注意が必要です。
原因の一つに、梅雨時はジメジメとしているので喉の渇きを感じにくく、水分があまり摂れていないことがあります。
1時間ごとにコップ一杯の水を飲む等、心掛けたいですね。
また、この時期は汗が蒸発しにくいことにも原因があります。
ストレッチやヨガなどで適度に身体を動かし、余分な水分を排出するのも良いと思います。
東洋医学的には、熱が身体に入ると、主に『心包』と『脾胃』に影響を及ぼすといいます。
心包とは、心臓を保護する膜のことで、血液の循環を調整します。
暑さによって体内に熱がこもってしまい、発熱やほてり、イライラなどの症状が出やすいです。
このようなタイプでは、十分な睡眠をとることが出来ないため、疲労が回復せずに夏バテが悪化しやすくなります。
脾胃は、胃や腸など消化器の働きに関わる器官です。
ジメジメした暑さにより、体内に熱や水分がたまりやすくなり、消化機能が低下します。
このようなタイプでは、食欲不振や軟便、下痢などが起こりやすくなります。
 熱中症の鍼灸治療法は、鍼治療によって体内の熱を下げ、気血の循環を助けます。
熱中症の鍼灸治療法は、鍼治療によって体内の熱を下げ、気血の循環を助けます。
お灸治療では、気血の流れを調節して症状を緩和させます。
また、漢方薬では『五苓散』が有効です。
むくみや、下痢、胃内停水、暑気あたりに用いられることが多いです。体内の水分の代謝異常を治癒するためこの季節に合った漢方薬の一つですね。
(ただし、漢方薬の処方は個人差があり体質によっても変わるので、漢方の相談ができる専門の医療機関や薬局などにご相談ください。)
そして、梅雨型熱中症予防におすすめの食材は、体内にたまった水分を排出しやすい、ゴーヤ、きゅうり、冬瓜、スイカ、小豆などです。
涼性の食材を積極的に食べて体に熱をこもらせないようにしたいですね。
水分をしっかり摂ることも大切ですが、冷たい飲み物をたくさん飲むと、胃腸を弱める原因にもなるので、
なるべく常温の飲み物をいただくようにしましょう。
梅雨型熱中症は、蒸し暑い時期に誰にでも起こりうる疾患です。
もし熱中症の症状が出たら、速やかに応急処置をして専門的な治療を受けることが大切です。
まずは熱中症にならないよう、しっかり予防し、元気な身体づくりを心がけましょう!
神戸東洋医療学院付属治療院
富田 彩
********************
神戸 三宮で鍼灸といえば
神戸東洋医療学院付属治療院
********************
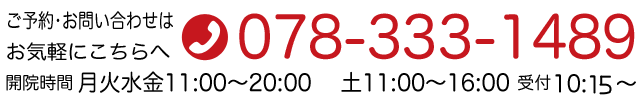
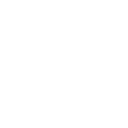
 今週から急に気温が下がり寒くなりました。
今週から急に気温が下がり寒くなりました。
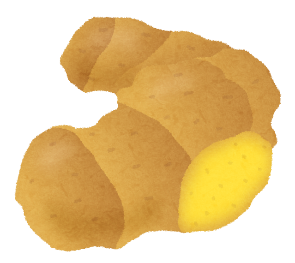 ショウガ、シナモン、ニラ、ニンニク、ナツメなど、体に熱を作り、体内の代謝を活発にする食べ物を摂取すれば、確実に体温を上げることができます。
ショウガ、シナモン、ニラ、ニンニク、ナツメなど、体に熱を作り、体内の代謝を活発にする食べ物を摂取すれば、確実に体温を上げることができます。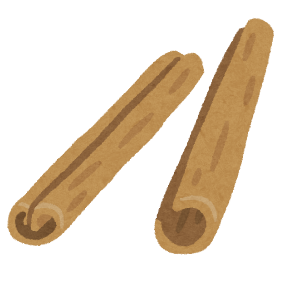
 有酸素運動と無酸素運動を並行した方が良いです。汗が出て息が切れるほどの中強度運動が効果的です。運動すれば、私たちの体は新陳代謝が活発になり、血液循環も円滑になり、体温維持に良いです。
有酸素運動と無酸素運動を並行した方が良いです。汗が出て息が切れるほどの中強度運動が効果的です。運動すれば、私たちの体は新陳代謝が活発になり、血液循環も円滑になり、体温維持に良いです。






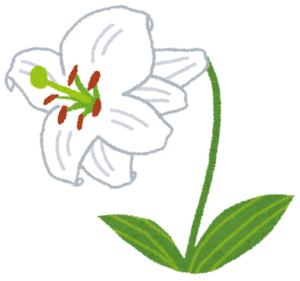


 芍薬の花は、凛とした佇まいに心惹かれる美しさがあります
芍薬の花は、凛とした佇まいに心惹かれる美しさがあります