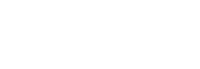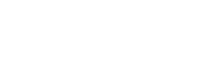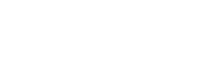カラダと水(補水と保水)
昨年の夏に続き今年の冬も水不足が深刻化しています。夏までに水不足解消を願うばかりです。
水は私たちの生活にとっても体にとっても必要不可欠なものです。
今回は「カラダと水(補水と保水)」をテーマに、水の大切さについてご紹介します。
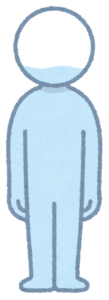
体内の水分は年齢によって変化します。
幼児は約80%、成人は約60%、高齢者になると約50~55%となり、体脂肪量や加齢による細胞の保水力低下に伴い減少します。
減少しながらも水分バランスを絶妙に調整しているのですが、水分が足りなければ脱水症状や熱中症の原因に。
逆に一度に水分を摂りすぎると水毒症(血中のナトリウム濃度が急激に低下)になり、いずれも頭痛やめまいなどの症状で体調を崩してしまいます。
症状が出なくても、一度の過剰摂取は心臓や腎臓の負担や、むくみの原因になるので十分に気をつけましょう。
一日の水分摂取量の目安は、飲料水からは約1~1.5リットル、食事に含まれる水分からは約0.8~1リットルとされています。
細胞は水分を一度に吸収できないのでコップ1杯ずつこまめに摂りましょう。
あくまで目安とされる基本的な水分量なので、気候、体格、体調、活動量(運動量)、食事内容(カフェインやアルコール、塩分量)、入浴時間など、その日の状態に合わせた水分量の調節が必要です。
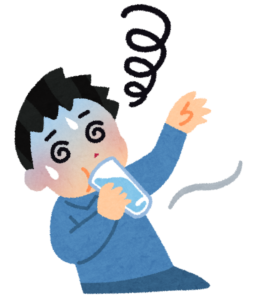
東洋医学では、水の影響を受けた体の状態を「陰虚(いんきょ)」や「水滞(すいたい)」といいます。
「陰虚」とは、体の水が不足することで体内の熱を冷ますことができなくなり、のぼせやほてり、喉の渇き、空咳、肌の潤い不足、便秘、痩せ気味などの症状や傾向が出やすいです。
辛い食べ物や飲酒は摂りすぎると熱を生み体の水を奪います。
長風呂やサウナなど大量に汗をかくことも控えましょう。
 「水滞」とは、水分代謝が悪く余分な水がたまることで、むくみや重だるさ、吹き出物、汗をかきやすく冷えやすい、むくみやすく太りやすい、軟便下痢気味などの症状や傾向が出やすく、雨の日や梅雨時期に不調になりやすいです。
「水滞」とは、水分代謝が悪く余分な水がたまることで、むくみや重だるさ、吹き出物、汗をかきやすく冷えやすい、むくみやすく太りやすい、軟便下痢気味などの症状や傾向が出やすく、雨の日や梅雨時期に不調になりやすいです。
お酒や脂っこいもの、甘いものを控え、腹八分で胃腸を労わりよく噛んで食べましょう。
入浴や運動で汗を流し、余分な水分を出しましょう。
体質、体調、年齢によって水分の摂り方は変わります。
より良く摂取するには、体内の保水力を高めるミネラル成分を多く含んだ食事と、保水する時間となる十分な睡眠が大切です。
バランスのよい食事と睡眠で、潤いのある身体を持続させましょう!
神戸東洋医療学院付属治療院
藤岡友子
********************
神戸 三宮で鍼灸といえば
神戸東洋医療学院付属治療院
********************
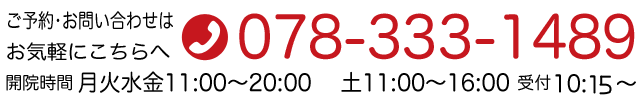
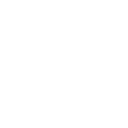
 東洋医学では、自然界の移り変わりと私たちの身体は密接に繋がっていると考えています。
東洋医学では、自然界の移り変わりと私たちの身体は密接に繋がっていると考えています。 ・温かい食事を摂る
・温かい食事を摂る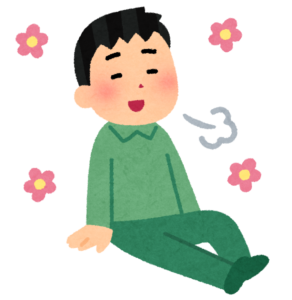





 保湿剤を選ぶ時は油分が十分なクリームや軟膏タイプがより良いです。
保湿剤を選ぶ時は油分が十分なクリームや軟膏タイプがより良いです。
 実は、この結核の治療に有効とされているのが、お灸です。
実は、この結核の治療に有効とされているのが、お灸です。